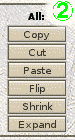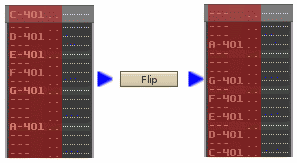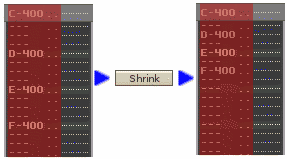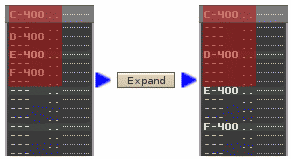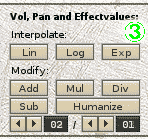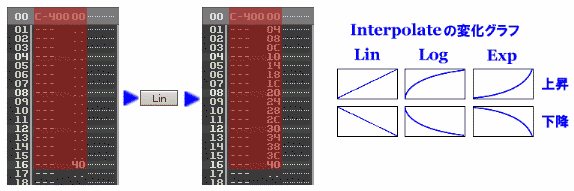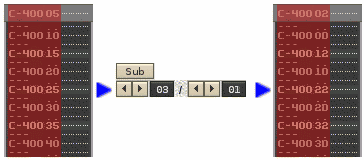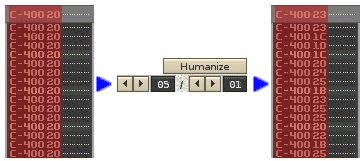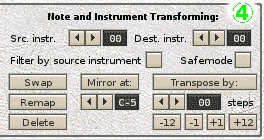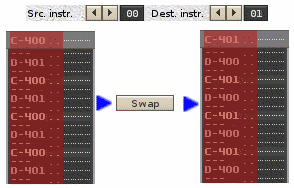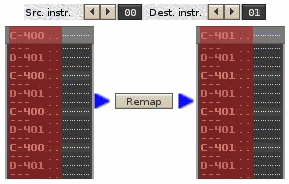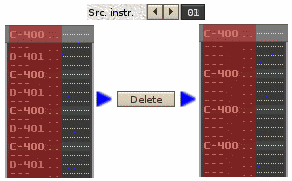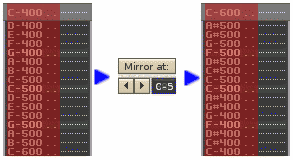『Unused instruments』 ・・・曲の中に一度も使われていない音色だけを削除します。曲が全て完成した時に一度押しておくといいでしょう。 『Unused patterns』 ・・・曲の中に一度も使われていないパターンだけを削除します。シーケンス画面でパターン番号を消しただけではデータは無くなりません。そういう裏側に眠ってしまったパターンデータを削除します。
DspChainとは、そのトラックに掛けた全てのエフェクター設定の事です。それぞれのパラメーター設定やエフェクトの順番をそのまま他のトラックにコピー&ペースト出来ます。 『Init』・・・initializeの略で「初期化」という意味です。この場合は使っているエフェクト全てを削除します。
そして残りの大きな部分がAdvanced Editの最も便利な機能群です。全てパターンエディット画面での打ち込み補助機能です。 大雑把に言うと、①で範囲を指定して、②~④の中から効果を選びます。では、それぞれの部分を細かく見ていきましょう。
次に右の7つのセレクターで、範囲内のどの項目に効果を与えるかを指定します。チェックを入れた項目すべてに効果が及びます。 コピー・カット・ペースト等、一般的な効果を選べる場所です。 『Flip』・・・選んだ範囲内の打ち込みデータの天地をひっくり返す、少し変わった効果です。ほとんど使わないと思いますが、何か面白いフレーズが生まれるかもしれませんね。 『Shrink』・・・1行(row)飛ばしで"行を間引く"機能です。データがスカスカな時にしか使えないでしょう。当然、行数が半分に減るので、この効果を使った区間はSpeedを倍にしないと元のテンポになりません。 『Expand』・・・Shrinkの反対で、1行(row)飛ばしで"行を追加する"機能です。さらに細かいエフェクトを掛けたい時などに使います。これは行数が倍になるので、この効果を使った区間はSpeedを半分にする必要があります。 『Interpolate』・・・「補間する」とゆう意味で、選択範囲の最初と最後に数値を打ち込んでこの効果を使うと、間の数値を自動的に入力してくれます。 『Modify』・・・「Add(足し算)」・「Sub(引き算)」・「Mul(掛け算)」・「Div(割り算)」です。 その数値は分数表示になっていて、左下の数字が「分子」・右下の数字が「分母」です。例えば、ボリューム等の値を半分にしたい時は「2/1」で割る(Div)か、「1/2」で掛ける(Mul)といいでしょう。単に3を足したい場合は「3/1」を足す(Add)でOKです。 また「Humanize」は機械的な打ち込み数値にランダムな変化を与えます。例えば「5/1」と打ち込んで「Humanize」すると、±5の数値変化をランダムに付けてくれます。 (左は-128~128・右は01~100まで入力出来るんですが、どんな時にマイナス数値を使うのか?等、今の所わからない事が多いです) 最後は音色番号の交換や、移調機能がある所です。 『Src.
instr.』 ・・・Source
instrumentの略で、元になる音色番号です。ここで指定した音色に効果を与えます。 『Dest.
instr.』 ・・・Destination
instrumentの略で、行く先とか目標になる音色番号です。SwapとRemap機能を使う時だけ指定します。 『Filter by
source
instrument』 ・・・TransposeとMirrorを使う時、ここにチェックを入れると、[Src.
instr.]で指定した音色番号にだけ効果が及びます。 『Safemode』・・・Renoiseが対応している音域は[C-0]~[B-9]までです。MirrorやTransposeを使った場合に、もしその音域を超えてしまう結果が出る時、その効果がキャンセルになるようにするボタンです。まぁ、そんな音域を使う事はほとんど無いと思いますが。 『Swap』・・・[Src. instr.]で指定した音色と[Dest. instr.]で指定した音色を交換します。 『Remap』・・・[Src. instr.]で指定した音色を[Dest. instr.]で指定した音色に変更します。 『Delete』・・・[Src. instr.]で指定した音色を削除します。 『Mirror
at:』 ・・・設定した音程を軸にして、それぞれの音程を上下に反転する感じです。 『Transpose
by:』
・・・移調機能です。12stepで1オクターブです。
|
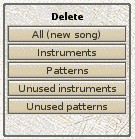 文字通り『削除する』機能です。ですから扱いには注意してください。
文字通り『削除する』機能です。ですから扱いには注意してください。
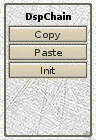

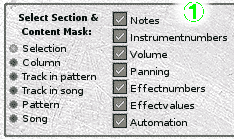 まず左の6つのセレクターで効果の及ぶ範囲を指定します。『Selection』はマウスでドラッグした任意の選択範囲の事です。
まず左の6つのセレクターで効果の及ぶ範囲を指定します。『Selection』はマウスでドラッグした任意の選択範囲の事です。